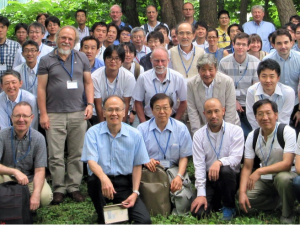学会ノート
追悼 Mayan
2021年07月27日
西浦 廉政
にしうら やすまさ
北海道大学
<出会い>
三村さんに最初にお会いしたのが,1972年に京都大学数学教室2階の計算機室だったと記憶している.学位論文作成に忙しいご様子で,タイプライターがカタカタと鳴っていた.前年に山口昌哉先生が主宰された岡村博「微分方程式序説」のセミナーに参加したのがきっかけとなり,私も計算機室に時々顔を出していた.初対面はかなり厳しい表情をされていた.抗原・抗体反応のモデリングと数値シミュレーションがそのテーマであったと記憶している.計算機室にはどういうわけか京大の所属ではない多くの若手・中堅研究者も出入りしており,おかげで分野と年代の異なる先輩達からアドバイスを得る機会を得た.ただ当時の私にとっては数学者のみならず,多彩な人物が門の向こうに待っているということはまだわかっていなかった.
<土曜セミナー>
定例セミナーは土曜に山口先生のお部屋で開催され,多くの人が出入りしていた.学部生の自分にとっては全く新しい世界で,様子がわかるまで時間がかかった.とにかくテーマが広汎で,数理生態学,特異点論,可積分系,偏微分方程式論,力学系,数値解析は当然としても,人文・社会科学にも軽々と飛び火するので,分野の垣根を取り払うには十分であったが,十分に理解できないものも多かった.寺本英,岡田節人,南雲仁一,広田良吾の諸先生から気鋭の経済学者塩沢由典氏まで,さらにルネ・トムら外国からの賓客も含め,ありとあらゆる人物が出入りし,議論していた.
<方程式の素性論>
方程式に貴賤はないのであるが,土曜のセミナー後にモデル方程式の素性論がよく俎上に上がった.出自がしっかりした,すなわち基本原理が確立したところから導出された方程式は素性正しきモデルであるが,現象論的方程式,とくに恣意性が高いと思われるものは評判が悪く,やり玉に挙がる.土曜セミナーではそのような材料に事欠かないので,エンドレスなディベートになることもしばしばであった.とくに数理生態学に関わるモデルの正当性や検証可能性は何度か議論に上った.三村さんはいつもその急先鋒だった記憶がある.当時は生命科学に関わるモデル方程式の検証可能性についての基盤は脆弱で,豊富なデータもなかった.三村さんの「現象数理学」へ至る道はここから始まったと思われる.
私自身はそのような議論を末席で楽しんでいたのだが,亀高 惟倫さんから「山口先生の哲学に惚れてはいけない,10年早い」と諭され,古典的な基礎文献の勉強を勧められた.グールサやピカールの古典的解析学教程に触れるきっかけともなった.当時は青焼き印刷で,西日の強い下宿では,すぐに消えて読めなくなるので慌てた記憶がある.脱線してしまった.
<黄金時代の広島>
1976年にOxfordのJames D. Murrayを訪問したのが,三村さんにとって大きな転機となった.数理生態学をどのように位置づけるかは,悩ましき問題であったと想像されるが,帰国後は問題の範囲も大きく広がり,迷いが吹っ切れたように見えた.私自身にとっても本格的に三村さんとの議論そして共同研究が始まったのはこの頃である.とくに1980年に広島大学に教授として赴任された後は,特異摂動理論を基礎として特異極限問題と界面方程式の枠組みにより多彩なパターンダイナミクスのモデリングとその解析に邁進され,大きな流れを作られた.
三村さんから助教授で広島に来ないかと言われたのが,1987年で,私は行くことを決心したが,実現までの2年間は多くの方に迷惑をかけてしまった.三村さんには当時の広島大学理学部長の菅原正博先生に京都にまでお越しいただく段取りを作ってもらい,広島に赴任後,すぐに菅原先生に挨拶に行ったが,お部屋で「まあ,座れ」と言われるやいなや書棚の奥からお猪口が出てきて驚いた.野武士のような菅原先生の破顔は覚えているが,お酒の味は覚えていない.
広島大学理学部数学教室は小講座制であり,三村研究室も良い意味での家内工房的まとまりがあり,暖かい雰囲気であった.テニスが大好きだった三村さんの強い影響で,研究室全体で週末はテニス大会がほぼ恒例だった.器用で勝負感の鋭い三村さんはコート上では別格の強さだった.私は赴任後しばらく自転車で東千田町から広島市内を数人であちこちを経巡った楽しい記憶が今でも残っている.昼飯をどこかで食べようと出たのはよいが,戻るともう夕方近くということも何度かあった.帰りによく立ち寄った鷹野橋近くの喫茶店房州(今はPoivriereというフランス風名前になっているようだ)のコーヒーの強い香りが今でも鮮明に残る.
80年代から90年代初めの広島時代は三村研究室の黄金時代であった.「いつも日本は周回遅れだ」と口癖のように言われていたが,周縁から中心が良く見えるということもあり,吸引力をもつ「場」の形成に注力されていた.Hodgkin–Huxley方程式の解の存在や安定性の結果も80年代後半のお仕事である.

多くの ワークショップ,セミナーに参加させていただいたが,強く印象が残っているのは,1989年の8月に大津市堅田で開催された第24回谷口シンポジウム「非線形偏微分方程式―理論とその応用」である,西田孝明さんと三村さんにより組織されたものである.非常にゆったりとした,かつ私のような若手には贅沢な国際会議であった.むろんそれは名前にある実業家(元東洋紡績社長)の谷口豊三郎氏の数学を含めた基礎科学振興への深い篤志によるものである.Andrew J. Majda,Jim Keener など当時の著名な研究者のみならず,アジアからの参加者もあり,その迫力は凄まじいものであった.これら多くの成果をひっさげて1990年の京都でのICM, 翌1991年ワシントンDCでのICIAMで三村さんは招待講演をされた.その後も枯草菌パターンや燃焼パターンをはじめ,三村さんの「形」の探求は続き,現在もその発展は続いている.
90年代に入ると東広島にキャンパスが移り,大学院改革が叫ばれるようになった.理学研究科でも新たな数学と生命科学を融合した専攻の設立に奔走されていた.あまりお手伝いしたわけではないが,概算要求のため夜中に当時の学部長先生のご自宅に草案を一緒に持っていった記憶がある.これは後に広島大学理学研究院に数理分子生命理学専攻が生まれる端緒となった.
1993年に東京大学大学院数理科学研究科に移られた.しばらくして1999年から代表者として推進された特定領域研究では特異性を軸に分野を超えた多くの研究者が集まる場となった.メンバーの半分近くは,物理の理論家や実験の研究者であり,数理モデルとは何なのか,という古くて新しい話題も再度浮上する機会が増した.私自身もこの頃から「贋作モデル論」を考えることとなった.
<イントロの書き方>
ムダをそぎ落としたエッセンスのみ書くスタイルが数学論文の基本であるが,応用数学ではそれと真逆のスタイルが必要だと,三村さんはセミナーでいつも学生に強調していた.つまりなぜその問題を考えるのか,そのモデル方程式と他のモデルとの比較など,そこに至るプロセスの記載がないと,だれもそんな論文は読まないというわけである.プレゼン練習ではいつも学生さんは絞られていた.歴史が浅く,群雄割拠の分野では,そのような位置づけなしには説得力がなくなるわけである.分野が成熟し ”On the shoulder of giants” の時代になれば,その前口上も不要となるのであるが,進化途上の分野では油断すると取り残されるという意識をたえずもっていたのである.
<三村共鳴>
矢崎成俊さんによれば120人以上の共著者との研究があるとのことで,それ自体驚きであるが,基本は人の懐に入る術数を自然に心得ているということであろう.会った瞬間の数秒の間合いで,その人とうまくやれそうかどうかわかると言われるが,三村さんはそのような瞬間の判断力,適応力は天才的であった.きっかけを作り,相手を引き込む力は「三村共鳴」と私は勝手に呼んでいる.例えば,雑談していて「今,こんなことやっているのだけど,聞いてくれる」と切り出して,10分ほどすると,真剣に自分もその問題を考えていることに気づくことがしばしばであった.
<現象数理学への道>
明治大学に移られてからは,「現象数理学」の拠点作りに奔走されていた.2007年に明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS)設立と同時に初代所長として着任され,その喜びは如何ばかりであっただろうか.モデルの素性論で激論を交わしていた頃のエネルギーはまだまだもっておられたし,MIMSは国内有数の共同研究拠点として成長しつつある今,もう議論ができないと思うと喪失感は大きい.
追記:文中,敬称は略させていただいた.また山口研では先輩であっても互いに「さん」付けで呼ぶのが習慣であったので,ここでもそのようにさせていただいた.親しい方々,特に外国のご友人はいつも三村さんを Mayan という愛称で呼ばれていたので,標題でもこの愛称を使うことにしました.その声を届けるためここで使わせていただいた.